つい先日、私が少年野球の現場で保護者
として、幼児教育の問題点を感じました。
あの手この手で入部してもらっても
受入体制ができてないと本末転倒です。
今日はこの辺りを書いていきます。
ぜひ最後までご覧ください。
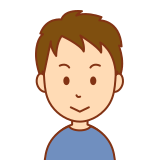
野球の幼児教育はいまだに軽視され
上級生優先は変わってないね。
『野球を始めたばかりの子に合わせた
練習や、メニューが殆どのチームで皆無
じゃないかなー。本当はここを一番充実
させることで、その後の成長や野球人口増
につながるんだけどね。』
◆入部したての子を軽視し過ぎ
◆入部したての子は別のメニューが必要
◆入部したての子こそ大事に
私の実体験を基にこういった疑問に答えます。
1.幼児教育の問題点3選
2.幼児教育が一番大事
この記事を書いている私は小学校1年生から
野球を始め、中学、高校、草野球と第一線で
20年以上のキャリアになります。
また、少年野球のコーチ、監督も歴任し
少年野球についての経験・実績は十分です。
そんな私の経験や、実体験をもとに
書いていきます。
幼児教育の問題点3選
今の野球離れの加速の要因として
幼児教育をできていないことが
あります。
ここをしっかりしていると幼稚園児から
入部させても安心です。
このあたりの今の少年野球界の弱点を
下記3点にまとめました。
✔いきなりの実戦
✔結果を焦る
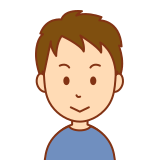
では、1点ずつ解説しますね!
✔幼児教育のメソットがない
ほとんどのチームで幼児教育にかける
時間や人員が不足しています。
どうしても4,5,6年生が主役となり
下級生は軽視されがちです。
しかし、この下級生こそ一番充実させて
シッカリと教える必要があります。
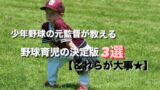
ここでの差が、その後の差となって
出てくるんです。
✔いきなりの実戦
捕る、投げる、打つなどの基本教育も
ないままにいきなり実戦形式に入れたり
します。
習うより、慣れろということなんでしょうが
幼児教育のメソッドが無いので、こんな
ことがおきます。
ここで一番悲惨なのはデッドボールが
当たったり、速い打球に当たったりして
ボールに対する恐怖心が芽生えることです。
ボールへの恐怖心が一度根付くと取り除く
のは至難の業です。
ボールへの恐怖心を植え付けないことが
一番大事になります。
✔結果を焦る
教えたから直ぐにできることと
できないことがあります。
それらを混同させて、結果を焦る指導者が
多いようです。
一度教えたから、言ったからできるはず、
という考えは危険です。
小さな子どもはできるようになるまで
根気強く指導することが大事です。
なかなか教えが伝わらないのは指導法に
問題があることがあります。
別の指導方法や、伝え方でアプローチ
していきましょう。
幼児教育の問題点って
本当にこれら3点でイイの?と思う方も
いらっしゃると思います。
幼児教育の問題点の大きな部分は
この2点が占めます。
ほとんどのチームがこれらのことを
やっているのが現状です。
ろくな指導もせず、できなかったら
怒られるのでは子どもはたまりません。
そんな野球界を変えるためにも
この幼児教育の問題点3点の改善が大事です。
ですので結論、幼児教育の問題点は
これら3点で大丈夫です。
野球界はまだまだ幼児教育の大事さに
気付いていません。
だからこそ、ここに力を入れているチームは
部員数や、上級生になっての結果などで
差が出てきます。
いち早く幼児教育の大事さに気付いた
日本一の多賀少年は他の追随を許さない
圧倒的な地位を築きました。
このように、幼児教育に力を入れている
チームが結果を出すことによって、他の
チームにも浸透すれば野球界としてプラスです。
こうして少しずつ、底上げができてくると
幼稚園からの入部も盛んになると思います。
サッカーはそれができていますから。
今回の振り返り、少年野球の元監督が思う
幼児教育の問題点3選【改善必須の重大課題】
は、下記になります。
✔いきなりの実戦
✔結果を焦る
これら3点が改善されていくと、
野球界も変わってくると思います。
幼児教育の部分って、現場が思っている
以上に保護者からすると比重が大きいです。
初心者をそう導いてくれるのか。そこを
入部しようか迷っている保護者は見ています。
そこに対する明確な答えを出せるチームが
伸びることでしょう。
というわけで、今回は以上です。
この記事が少しでも少年野球関係者の為に
なれば幸いです。
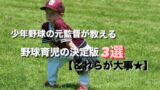
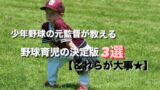
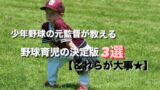






家遊楽賢 ~家族で遊ぶ、楽しく賢く♪~


